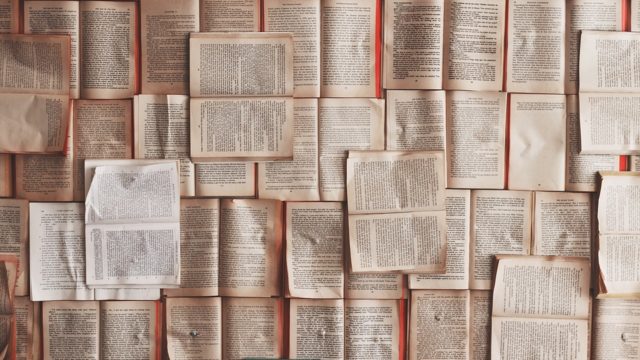書籍「デス・ゾーン」/河野啓
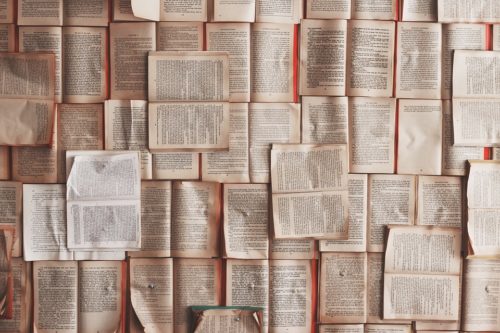
【書評】★★★★☆(85点)
この本をお薦めしたい方
誰が読んでも面白いノンフィクションだが、あえて言えば、自分以外の何者かになろうとしている方は読んでみると、足元が固まっていいのではないだろうかと思う。
この本は、特に「内向型」「外向型」の軸で読むとさらに面白い。便宜上「内向型」「外向型」と二項に単純に分けた上で本記事は書くことにするが、例えば、判断の基準を「自分の中に持つ者」「他者に持つ者」など、うまく読み替えてほしい。それぞれの性格特性は代表的なものではあるが、誰もがグラデーションのように両特性を少なからず持っており、単純に分割できないし、あまり属性に自分を寄せすぎて決めつけてほしくもない。
そして、隙間産業のような当ブログの読者は、内向型であれ外れ値だろうし、外向型であれば、さらにレア度の高いハイブリッドの可能性が高い。きっと言語を獲得している方が多いと思うので、拙くともうまく読んでくれると信じている。
本書は是非読んでもらいたいので、内容はあまりネタバレせず、栗城史多氏の人物像への考察と、残された動画等から個人的に感じることを書いていきたい。
内向型と山
私は、彼の存在自体は知っていた。昔参加していた、登山サークルで度々話題になったからだ。内向型である私と山との関係は薄く長い。幼少期から家族に連れ回されて色々な山を登った。父親は山歩きのなかで、根気強く私の内股を矯正し、よく背負子に乗せてくれた。
道具を用いるような本格登山というものは経験したことがなく、山小屋に宿泊したこともない。日帰り登山が主で、全くの素人でもないが、経験者というのもおこがましい。岩場に関しては、ボルダリングをやっていた関係で、ルートクライミングを少しやったことがあるが、ロープ張りも結びもおまかせが常で、ビレイヤーに上げてもらうような殿様クライミングだった。岩場の高いところは楽しいが怖い。
一時期参加していた登山サークルは、大人になってから登山始めましたというような、にわかのおじさんがリーダーだった。冬でもとにかく、野外料理に固執し(止まるとめちゃくちゃ寒い)、栗城氏推しだった。体力があまりない私は、その感性と行程に疑問があり、そのうちそっと離れた。山の経験が豊富な私の母親は、あまりその人達と本格的な山には行かないようにと言っていた。
団塊世代が経験した山ブームでは、今のようにちょっと噛じるという発想がなかったようだ。母親は天気図を読む訓練をし、行程表をしっかり作成して登山していたらしい。今、再び山ブームが起きているが、危うくなったなと私自身も感じている。
とは言え、安全に楽しむ限り山はいい。内向型にはピッタリの場所だろうし、かつての山男山女と言えば、そういう人が多かったのではないだろうかと思う。わたしはどちらもやるが、海へ向かう者と、山へ向かう者はやはり違う。
ついでに、かなり話がそれるが、婚活している内向型の女性に、山男は心からお薦めだ。ボルダリングや、にわかキャンパーのウェイ系ではない。ひと括りにはできないが、本格登山を経験している山男に金脈がある。感性の違いは内向型にとって超えられない壁のひとつだが、彼らが自然にアンテナを巡らせ、体力のない者に合わせてルートを選び歩調を整える様子は、そういう意味でもとても頼もしい。そして何より、山を登るというのは、まぁ普通に楽しく会話もするのだが、自分と向き合う時間が一番長い。そういう人間は信頼できる。
栗城史多(くりきのぶかず)という人間
私が栗城史多氏について覚えていたのは、「7サミッツ」というキャッチーな単語と、凍傷で指を失ったことと、ついにはその生命を失ったことだけだ。
意外にも、本人が繰り返し使用していたらしい「単独無酸素」という言葉は全く覚えがなく、本を読んで初めて知った。そもそも彼をしっかり映像で見たことが1回ぐらいしかない。彼が人気者になってからだと思うが、インタビューに応じていたであろう映像は、内容も覚えていないし、一瞥しただけで興味が全く沸かなかった。
これは、内向型の方にはもしかしたら共感いただけるのではないだろうか。まず、彼の目が信用できないことと、言葉が拙すぎるために、即座に私のなかでは「取るに足らない人物」となった。忌憚なく書くならば、このノンフィクションで書かれていた結末は「お調子者の成れの果て」でしかなかった。
本書はとても面白かったが、読了後も栗城史多氏には興味が全く持てなかった。関連映像を2~3確認して、仮説の確認をしたら気が済んだ。史多(のぶかず)という名前も、何度も読めなくなる。そして多分、この記事を書き終えると永遠に読み方を忘れる。
何者かになりたい者
栗城氏を一言で表すならば、私はこう書く。「何者かになりたかった者」だ。
これはとても不思議な感覚だ。私は自分以外の何者かになりたいという思いを抱いたことがない。私は私でありたい。
少し考察を深めてみる。その感覚を知らないとは言え、特別な存在になりたいと考える人間が多いことは理解している。そして、「誰かにとって特別」ではなく、「Allにとって特別」という不遜さだ。内向型の私に言わせてみると、これはマジョリティの傲慢だとも思う。
「マジョリティの特権は失わずに、マイノリティ側に落ちることなく、周囲の耳目や尊敬を集める、強く煌めく個性的な存在でありたい」ということだろうと思うのだ。
例えば、内向型は生まれつき個性的なことが多く特別と言えば特別だが、同時にマイノリティとしての生きづらさを伴っているため、あまりそこに感謝したことはないのではないか。そういった面倒な立場はきっと栗城氏は嫌だろう。誰にも蔑まれることなく、多くの者に受け入れられるが、個性的でもありたいという矛盾した思い。多くのお調子者によく見られる特性で、どうしようもない。
そもそも、お調子者がよく言う「個性的」とは「目立つ」「派手さ」という意味に寄り過ぎてはいないだろうか。やはり数が多いゆえかもしれないが、突出して叩かれるのは嫌だが、ちょっと優位に立ちたいという小物感が透けて見える。
彼は登山家ではないだろう。自称も他称も何でもいいが、彼はずっと特別な何かになりたかっただけの、ちょっとプレゼンが上手かったワナビーだ。もし、この時代にビデオカメラがなかったら、栗城氏は登山をしなかっただろう。彼にはいつでも観衆が必要で、裏を返せば、自分のなかにしっかりとした軸や動機がない。何かをやり遂げる者は、誰が見ていなくともやる。
おそらく彼を突き動かしていたのは、「人気者になりたい」「有名になりたい」という欲求であり、山はその手段に過ぎず、彼は登ることさえあまり好きではなかったように思う。それでも、こう言っては何だが、そんなもののために、腰まであるような雪をかき分けて一歩一歩登る様子は大したものだなと思う。
最後のインタビュー
栗城氏の人間性を考察する上でとても有用なので、最後のエベレストチャレンジ直前のインタビュー映像(2018.03)を紹介したい。
私はまず、彼の存在の小ささに驚いた。彼の中に自信がまるでない。高揚感もなく、これから大きな挑戦をするとはにわかに信じがたい。そして、質問に応答する語尾に着目してほしい。文言を閉じる際、必ずと言っていいほど、彼の視線が泳ぎ語尾の音程を調整する。彼の前にはスタッフが3名ほどいるようだが、媚びるような視線を巡らせる。何度も不必要に挟まれる笑顔にも違和感がある。彼は、自分を表現しようとするのではなく、ウケるように演出しようとしている。伺うような視線は、どの程度で相手を自分のペースに引き込めるか測っているような下品さだ。
こういう人間は要注意だ。本心や自分の考えを答えずに、相手を喜ばせようとしたり、嘘でうまく切り抜けようとする。どうにも危うさを感じる。
そして、これは彼の全盛期から変わっていないが、言葉に重みがない。ところどころキラキラした言葉を用いるが、どうにも空虚で、借り物という以外に何も感じない。声に魔力がなく、響いてこない。極限まで向き合った登山家から出る言葉とは到底思えない。栗城氏は登山家の行動を同じように辿ったかもしれないが、彼らがあえて言及しないが必ずやっている「自分自身と向き合う」ことをやらなかったため、言語を獲得しなかったのだろうと思う。申し訳ないが、私はこのような人間を信用しないし、興味がもてない。
注目を浴びていたいという思い
彼について厳しいことを多く述べたが、悲しい側面がひとつある。それは彼が渇望し続けた耳目への強い欲求だ。
多く残された自撮り映像や最後のインタビューからも、彼には観てもらいたいという思いが相当強い。衆目がなければ動き出せないのではないかと思うくらいだ。彼の多用していた言葉「夢の共有」、それが力になると言えば聞こえは良いが、自分ではもはや自分を支えきれなかったように思う。自分が本当にしたいことも分からなかったのではないか。もしくは、「有名になりたい」「観ていてほしい」という思いだけでは、次の一手がもう思いつかなかったのかもしれない。
これは邪推が過ぎるが、早くに母親を亡くしていることが大きいのではないかと思う。彼の残した映像からは「見て!見て!見て!」というような悲鳴が聞こえてくるようだ。
私自身は、目立つことが嫌いで「そっとしといて」と思うタイプなので、どうもこの感覚がうまく想像できないが、この「目立ちたい」「見てほしい」という感情には、何か根っこがあるようで気になる。寂しさだろうか。
彼はとても多くの人間に愛されていたのに、それでは足りなかったのだろうか。唯一と言える女性がそばに居たようなのに、それさえも手放してしまう。より多くの衆目、より多くの金銭的援助、増え続けるそれらがなければ、物足りなかったのだろうか。彼の挑戦をずっと見守り、残されたお父様の心中を思うと苦いものがある。等身大で愛されるとは、なんとも羨ましいことなのに、その恵まれた自分の存在を省みることはなかったのだろうか。
彼自身は、否定された壁をぶち破るという表現をしていたようだが、私は、彼のファンは、彼が登山を楽しんでいないことに失望し、応援できなくなったのではないかと感じている。別に登山ではなくとも、彼が心から楽しいと思えることをやっているならば、応援する人間はいくらでもいたし、新しくファンになる者も多かっただろうと思う。ファンの思いは、「夢を背負って叶えて」ではなく、「本当に好きなことをやってほしい」ではなかったか。結局のところ、彼は等身大のままで愛されるという自分自身をまったく信じていない。
もし彼に会ったら聞いてみたいことがひとつだけある。
「嘘をつかなかったこと、あるの?」
栗城氏は、自分自身とかけ離れた自己像を演出しすぎたために、誰にも弱音を吐けず、自らを追い込んでいったような節がある。彼の人生において、素直な自分自身をさらけ出し対話することはあったのだろうか。恋人であれ、自分自身であれ。母親に対してだけ、それができたのだろうか。
そして、一気に脚光を浴び称賛され、一瞬であろうと他者の承認軸で生きた人間は、本人にその自制と、周りのサポートがとても重要だとも感じる。周囲に耳の痛いことを言える人間を配置できるか、また、それを聞けるかは、本人の器によるところが大きいが、そのせいばかりにもできない。誰でも経験したことのない称賛を一気に浴びると、自分の大きさ、存在、目的を勘違いしてしまうものだろう。この消費社会は、定期的にピックアップした人物にスポットライトを当てて、人工的に輝かせては放り出すようなことを繰り返しており、何とも無責任だ。
うっかり未成熟のままに観衆のパワーに当てられてしまうと、誰にでも栗城氏のようなことが起こりうるのではないかと思う。特に芸能人の方には気をつけてほしいし、そのような演出が減ることを願っている。